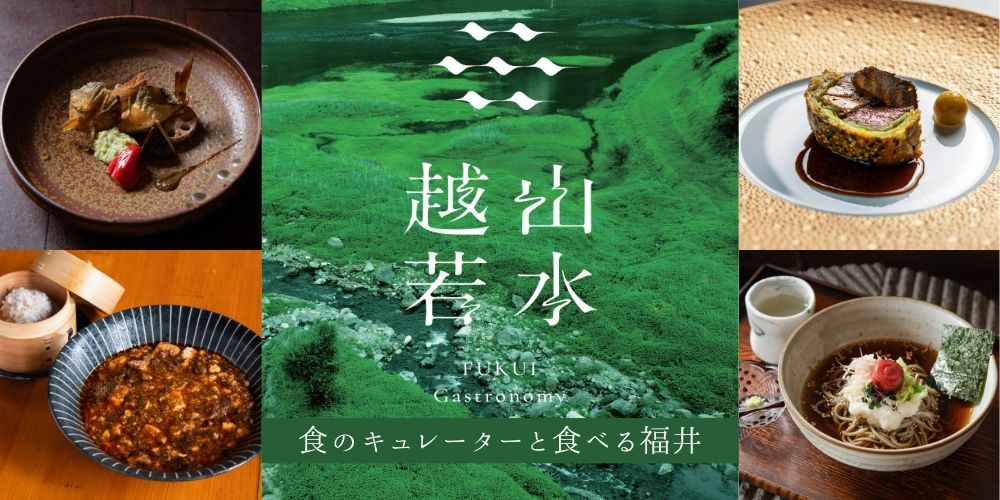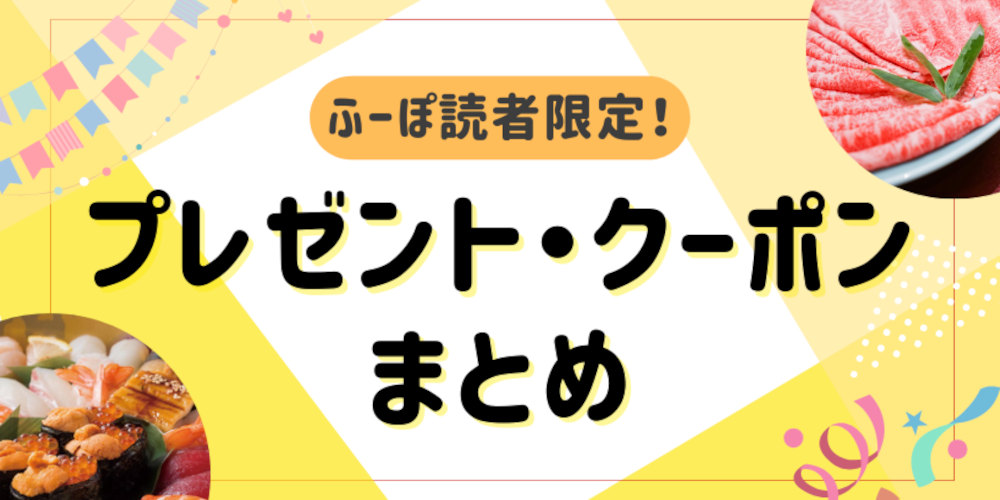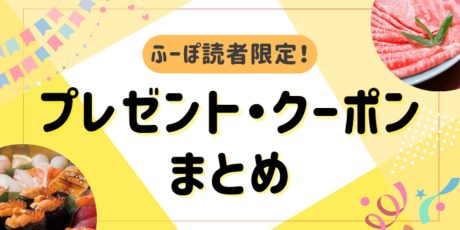高校時代の友人から久しぶりに連絡があった。
福井で過ごしていた頃は四六時中、夢を語り合う仲だった。
やがて彼は東京へ。
僕は地方の大学へ進んだ。
大学生になって初めての正月。
帰省した福井で、片町に一軒だけあったディスコで再会した彼は、みんなが当時流行りのDCブランドで全身を固めていたなか、ひとりビンテージのリーバイスにアディダスを履いて、古着のスウェット、スケボー片手に現れた。
そこにはまだ誰も知らなかったヒップホップやクラブカルチャーの匂いが漂っていた。
* * *
その後、僕は編集者を目指して上京し、彼はレコード会社へ。
同棲していた彼女に追い出された時は僕のおんぼろアパートに転がり込んできてしばらく一緒に暮らしたこともあった。
「Technics SL-1200のターンテーブル」「スクラッチ」「藤原ヒロシ」「ロンドンナイト」。
最先端のファッションやクラブシーンをたくさん教えてくれた。
僕が結婚した時には彼の会社でプロモートしたミュージシャンの「Happy Wedding」のサイン入りレコードをプレゼントしてくれたなあ。
* * *
時が流れ、ロンドンでレコードプロデューサーになりたいという夢を叶えることはできず、福井に戻ったというのは知っていた。
そんな彼が懐かしい「五月ヶ瀨」片手にひょっこり顔を出したのだった。
* * *
かつてのおしゃれ番長の面影はなく、いまは福井に暮らしながら、全国の認知症患者の家族を支える社団法人を運営しているという。
その転身ぶりにまずびっくりした。
実は僕自身も、母がまだ元気だった頃、急に僕のことを自分の弟と間違えたり、その場にいない人のことを語り出したりする姿に戸惑った経験がある。
とても心配になって、渋る両親を「もの忘れ外来」に無理やり連れて行ったところ、すぐに「認知症」と診断されてしまった。
母はひどく落ち込み、肩を落とした。
もう生きていても仕方ないという絶望感からなのか程なくして腎臓と糖尿病が同時に悪化して入院。
それっきりだった。
果たしてあの判断は正しかったのだろうか。
いまもずっと自問し続けている。
* * *
認知症患者を抱える家族の大変さは僕に語ることはできないが、そうした人たちを支えるために自分の時間を惜しみなく差し出している彼の活動には心から頭が下がる。
自分の未来と時代を必死で追いかけていた彼が、いま人に寄り添うことを選んでいる。
* * *
僕自身も含め、人生は思い描いた道をそのまま歩けるわけではない。
むしろ予期せぬ流れに押し流されて、ようやく立ち止まれる場所にたどり着くのかもしれない。
友人が渡してくれた五月ヶ瀨の懐かしい甘さを口にしながら、そんなことをしみじみと思った。

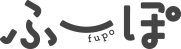


 編集者・著者。福井県出身。扶桑社発行の雑誌「天然生活」「ESSE」元編集長。石田ゆり子著「ハニオ日記」(扶桑社)、「保護犬と暮らすということ」(扶桑社)などを編集。犬1、猫4と暮らす。釣り好き。著書「妻が余命宣告されたとき、僕は保護犬を飼うことにした」(風鳴舎)が好評発売中。集英社「よみタイ」にて連載した「真夜中のパリから、
編集者・著者。福井県出身。扶桑社発行の雑誌「天然生活」「ESSE」元編集長。石田ゆり子著「ハニオ日記」(扶桑社)、「保護犬と暮らすということ」(扶桑社)などを編集。犬1、猫4と暮らす。釣り好き。著書「妻が余命宣告されたとき、僕は保護犬を飼うことにした」(風鳴舎)が好評発売中。集英社「よみタイ」にて連載した「真夜中のパリから、